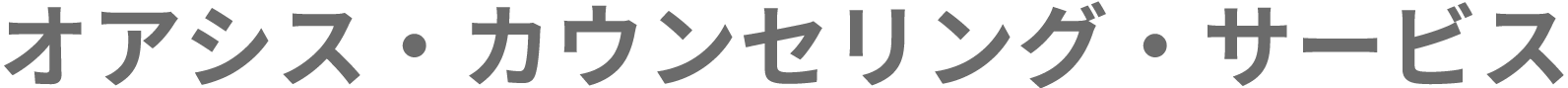上司の部下とのコミュニケーション【アクティブリスニング】の方法

従業員のメンタルヘルス対策が、多くの企業・団体・施設に重視される時代となりました。今回の記事は、上司の部下とのコミュニケーション、特に「アクティブリスニング」(積極的傾聴)のスキルに焦点を合わせて解説します。
職場内でのコミュミケーションにおいて、何をどう話すかも大事ですが、それ以上に大切なのは「聴く」ことです。しかも、漫然と「聞く」のではなく、「聴く」、すなわち明確な意図を持って積極的に耳を傾けることによって、相手との信頼関係が増したり相手のメンタルヘルスが向上したりします。
特に指導的な立場である上司にとって、部下の話を「聴く」ことは非常に重要なスキルです。部下とのコミュニケーションに悩んでおられる方は、ぜひ参考になさってください。
目次
上司の対部下必須スキル「アクティブリスニング」とは何か

アクティブリスニングは、相手の話に積極的に耳を傾け、相手を理解しようとするコミュニケーションスキルです。この手法は、心理カウンセリングで用いられる技法として知られていますが、職場や家庭などあらゆる人間関係を円滑にするうえでも非常に有効です。
もちろん、上司が部下とコミュニケーションを取る際にも、非常に有効です。
なぜ上司の部下とのコミュニケーションで「聴く」ことが大事なのか
上司は、部下にさまざまな指示を与えたりアドバイスをしたり、時には叱責を与えたりします。すなわち、「伝える」ことが重要な仕事のはずです。それでも、部下の話に積極的に耳を傾ける、アクティブリスニングを実践することが大切なのです。
なぜでしょうか? それは、上司が部下にアクティブリスニングを重視したコミュニケーションを取ることで、以下のような効果が生まれるからです。
(1) 部下に信頼される
信頼できない人からどんな正論を吐かれても、喜んで実践しようとは思えません。こちらの話を積極的に聴いて欲しければ、まず信頼関係を深める必要があります。
上司であるあなたがアクティブリスニングを実践すると、部下は「この上司は私の話をちゃんと聴いてくれる。だから、信頼できる人だ」と思えます。そして、あなたの話にも真剣に耳を傾け、指示やアドバイスを喜んで実践してくれるでしょう。
(2) 部下に適切な「伝え方」ができる
誤解や情報不足の状態で行なうアドバイスや指示は、的外れになってしまう可能性があります。
上司であるあなたが部下の話をよく聴くことで、誤解が生じる可能性が減りますし、部下を取り巻く状況についてより詳しく知ることができます。その状態で行なわれるアドバイスや指示なら、より適切なものになるでしょう。
アクティブリスニングのスキル

特に、以下のポイントに留意しながら話を聴きましょう。
(1) 相手の話をさえぎらない
こちらが何を話すかということより、まずは相手の話を聴くことに徹します。言いたいことが生じても、相手の話の腰を折らず、最後まで聴いてから話すようにしましょう。
(2) 「聴いているよ」というサインを出す
「話の腰を折らない」といっても、ただ黙っているだけだと、相手は「本当に聴いているのか」と不安になります。ですから、聴いているというサインを出しながら聴くことが大切です。具体的には以下の3つのサインです。
1) アイコンタクト
相手の目を見ながら。
スマホやPCの画面、あるいは書類を見ながら人の話を聴いていませんでしたか?
2) うなずき
真剣に聴こうとするあまり、うなずくのを忘れないようにしましょう。
3) 相づち
「ふーん」「そうなんですね」「へー」「なるほどー」など、何かしら声を出しながら。
電話だとアイコンタクトやうなずきは相手に伝わりませんから、相づちを大きな声ではっきりと打つ必要があります。
なお、私がメンタルヘルス研修でアクティブリスニングについて教える際は、座学だけではなくロールプレイを行なっていただきます。
その中で、上述の3つの「聴いているよ」のサインを、あえて入れないで話を聴く体験をしてもらいます。つまり、相手を見ず、一切体を動かさず、うんともすんとも言わずに聴くのです。
話し手と聴き手を交代しながらそのワークをやっていただくと、参加者の皆さんからは「3つのサインがいかに大事か痛感した」という感想をいただきます。
(3) 気持ちに焦点を合わせる
「次に自分が何を話そうか」ということを意識するのではなく、まずは部下の話に意識を向けましょう。特に、相手の気持ちとそう感じる理由に焦点を合わせます。
- この人が話をしているそのエピソードの中で、この人はその時どんなふうに感じたのだろう?
- その話をしながら、この人はどんな気持ちになっているのだろう?
- そして、なぜそう感じるのだろう?
というのも、人が相談をしたり、愚痴をこぼしたり、弱音を吐いたりするのは、「自分の気持ちを分かってほしい」「そう感じるもっともな理由があるから、それを分かってほしい」と思っているからです。
部下が上司であるあなたと面談した際、相談・愚痴・弱音を吐いたとします。その部下は、もちろん今抱えている問題を解決したいと思っていますし、解決するためのヒントが欲しいとも思っています。しかし、それ以上に「分かってほしい」という欲求の方が、優先度が高いのです。
ですから、まずは部下の気持ちと理由を聴き取りましょう。そして、部下の気持ちと理由が伝わってきたら、「それはがっかりしたよね」「それはつらかったでしょう?」などと気持ちに寄り添ったり、「こういう理由があるなら、そんなふうに感じるのは当然だよ」と理由を受け止めたりします。
そうするなら、部下は「分かってもらった!」と感動し、満足し、「じゃあ、今度はあなたの話を聴かせて欲しい」という精神状態になれます。
それをしないうちにこちらの話を聴いてもらおうとしても、なかなかうまく行きません。カウンセリングの基本的な技法を確立したカール・ロジャーズは言いました。「直そうとするな、分かろうとせよ」。
まずこちらが聴き、気持ちに寄り添い、それからこちらが話す、という順番を意識しましょう。
気持ちに寄り添う言葉かけ 7つの例
気持ちに寄り添う言葉かけとして、さまざまな状況で使える汎用性の高い7つのフレーズを紹介します。部下が気持ちを語ってくれたときに使ってみてください。
- 『そうだよねぇ』
- 『それは~だよねぇ』……「~」には相手の気持ちを入れます
- 『それは~でしょう?』……「~」には相手の気持ちを入れます
- 『それはそうだよ』
- 『そう感じるのは当然だよ』
- 『本当だよねぇ』
- 『それくらい~だったんだよね?』……「~」には相手がそう感じた理由を入れます
私が行なうメンタルヘルス研修では、これらの「気持ちに寄り添う」(共感する)スキルについて、ペアになってロールプレイしていただいています。かなり盛り上がり、終わると皆さんすっきりした表情になります。相談者役として共感してもらう体験をするからでしょう。
そして、それによって、部下の話の腰を折らずに最後まで聴き、気持ちに寄り添うことの大切さを実感なさるようです。
(4) 非言語の情報にも注意を向ける
人間は言葉だけでなく、身振り手振りや表情、声のトーン、間の取り方などで、さまざまな情報を発信しています。たとえ沈黙している相手でも、よく観察したり、それまでの話の流れを振り返ったりすれば、さまざまな「心のつぶやき」が聞こえてくるはずです。
(5) 評価しないで聴く
誰しも自分なりの好みや価値観があります。それは大切にしてください。しかし、相手の話を聴くときには、それらはいったん脇に置きましょう。
すなわち、自分の好みや価値観で相手の話の良し悪しを評価しないで、「とにかく相手はこう言っているんだな」「相手はこう感じているんだな」「相手はこのように行動したのだな」と受け止めます。
アクティブリスニングの例

部下:「今、家内の体調が悪いので、早めに帰って家事を担当したいんです。今週は残業しないで定時上がりにさせてもらっていいでしょうか?」
△上司:「わかった」
定時上がりでいいかどうか許可を求められたのですから、本来ならこの回答で問題ないはずです。しかし、何だか冷たい印象を覚えないでしょうか?
では、「妻のことが心配だという気持ち」や、「でも同僚たちが忙しく働いているのに自分が先に帰ることに対して申し訳ないという気持ち」に寄り添った対応をするとどうなるでしょうか。
○上司:「わかった。仕事のことは心配しないで奥さんに寄り添ってあげなさい。そういう事情なら、みんな進んでカバーするから。でも、奥さんのこと心配だよね。早く良くなるといいね」
きっと部下は、こう言ってくれた上司のことをこれまで以上に信頼するようになるでしょう。
上司から部下へのアクティブリスニングが職場にもたらす効果

上司が部下にアクティブリスニングを実践すると、職場にどのような変化が生まれるのでしょうか。メンタルヘルス研修に参加した須賀川市の企業担当者からは、以下のような感想や体験談が寄せられました。
(1) 信頼関係の構築
アクティブリスニングを通じて、上司と部下、従業員同士、社員と顧客の信頼関係が深まります。
(2) 離職率の低下
職場のコミュニケーションが改善し、従業員の満足度が向上した結果、離職率の低下が期待できます。
(3) 生産性の向上
上司と部下、従業員同士、顧客とのコミュニケーションがスムーズになると、無駄な衝突や停滞を防ぎ、業務効率が向上します。また、会議などで安心して発言できるようになるため、次々と新しいアイデアが生まれるようになります。
メンタルヘルス研修参加者の感想

私が行なうメンタルヘルス研修では、理論の講義だけでなく実践的なワークショップにも力を入れています。聞き手や話し手として実際にアクティブリスニングを体験することによって、多くの気づきが得られます。
たとえば、受講生の方々からは次のような感想やコメントをいただいています。
(1) 沈黙が怖くなくなった
「これまで、部下が沈黙してしまうと、何かしゃべって間を埋めないといけないと焦っていました。しかし、こちらが何を話そうか気にするのではなく、相手の気持ちとその理由に焦点を合わせるようにしたところ、沈黙が怖くなくなりました。」
(2) 評価しないで受け止めることの大切さを知った
「相手の話を自分の気持ちや価値観で評価しないで、ただ聴くというのは難しかったです。しかし、自分が話し手の立場だったら、いちいち評価されたのでは安心して話せません。ですから、自分も自分の思いを(捨てるのではなく)脇に置いて受け止めようと思えました。」
(3) 部下が話しかけてくれるようになった
「これまで、部下から報告や相談を受けると、上司なんだからと意気込んでで、すぐにあれこれ説教したりアドバイスしたりしてきました。しかし、研修を受けてからまず聴くことを優先するようにしたところ、これまで以上に部下が話しかけてくれるようになりました。結果として、必要なアドバイスも的確にできるようになり、以前よりチームの成績が向上しました」
(4) 聴いてもらってすっきりした
「研修の中で行なったロールプレイで、話を聴いてもらう体験をしたのがよかったです。気持ちに寄り添いながら最後まで話をじっくり聴いてもらえるだけで、こんなにも心がすっきりするのかと、改めて驚きました。私も部下や家族の話にじっくり耳を傾けたいと思います」
まとめ

アクティブリスニングは、相手との信頼を築き、コミュニケーションを改善するための強力なスキルです。研修を通じて多くの参加者がその効果を実感し、職場や私生活で実践したいという声が多数寄せられました。
私は、福島県須賀川市や郡山市を中心に、福島県内や宮城・栃木・山形など近隣県の企業・団体・施設で、メンタルヘルス研修を行なっています。特に、「上司の部下とのコミュニケーション」に関する講義は非常に人気が高く、ロールプレイの時間は大変盛り上がります。
ぜひ貴社でも、「上司の部下とのコミュニケーション」や「アクティブリスニング」をテーマとした研修をご検討ください。全力でサポートさせていただきます。お問い合わせは、以下の公式サイトからお気軽にどうぞ。
→ オアシス・カウンセリング・サービス公式サイト