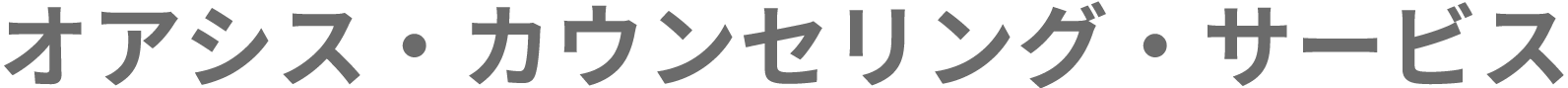【職場の適応障害とは?】その原因・症状・対策:メンタルヘルス研修@須賀川市

近年、職場でのストレスが原因で心身の不調を訴える人が増えています。その中でも「適応障害」は、多くの人が悩むメンタルヘルスの問題の一つです。適応障害は、環境の変化やストレス要因に適応できずに心身のバランスを崩す疾患であり、放置すると深刻な影響を及ぼすことがあります。
本記事では、適応障害の症状や原因、うつ病との違い、治療方法、そして職場における対応策について詳しく解説します。
なお、私は福島県須賀川市を拠点に、郡山市や福島市など福島県内、また山形、宮城、栃木など近隣県で企業・団体・施設様でメンタルヘルス研修を行なっています。この記事は、研修で適応障害についてお話しした際によくいただく質問を元に構成しています。
目次
適応障害の症状は?

適応障害の症状は、主に精神的・身体的・行動的な側面に現れます。個人差はありますが、以下のような症状が一般的です。
精神的な症状
- 強い不安感や抑うつ状態
- 怒りやイライラの増加
- 集中力の低下
- 絶望感や無力感
身体的な症状
- 頭痛や胃痛
- 倦怠感や疲労感
- 不眠や過眠
- 動悸や息苦しさ
- 特に理由も無い涙
行動的な症状
- 過剰な飲酒や喫煙
- 遅刻や欠勤の増加
- 仕事のミスや能率低下
- 社交的な活動の回避
このような症状が、ストレス要因に対する反応として明確に現れ、仕事や日常生活に影響を及ぼす場合、適応障害の可能性が考えられます。
重度になると働けなくなりますから、このような症状が現われたら、「まだ頑張れる」などと一人で抱え込んだり我慢したりせず、医療機関を受診しましょう。
適応障害になると働けますか?

適応障害を抱えた場合、働けるかどうかは症状の程度や職場環境によります。軽度であれば適切なサポートを受けながら仕事を続けることも可能です。しかし、重度の場合は休職が必要になることもあります。
働き続けられるケース
- 症状が軽く、業務に大きな支障がない
- 上司や同僚の理解があり、業務負担を調整できる
- ストレスの原因を軽減する対策が取られている
休職を検討すべきケース
- 強い不安感や抑うつ状態が続く
- 業務遂行が困難でミスが増える
- 体調不良が頻発し、欠勤が多くなる
適応障害で休職するかどうかの判断基準は?

適応障害の休職を検討する際の判断基準には、以下のポイントがあります。
- 医師の診断:診察を受け、医師の意見を参考にする
- 業務遂行能力:仕事を継続することが困難かどうか
- 職場環境の調整可否:ストレス要因を軽減できるか
- 症状の程度:心身の不調が深刻か
休職は最後の手段ですが、適切な時期に休むことで回復が早まることもあります。一方、無理に働き続けることが症状の悪化を招く可能性があります。医師や上司などと相談の上、適切な対応を取ることが重要です。
適応障害とうつ病の違いは?

適応障害とうつ病は似た症状を持ちますが、明確な違いがあります。
| 項目 | 適応障害 | うつ病 |
|---|---|---|
| 原因 | 明確なストレス要因がある | さまざまな要因がある |
| 症状の持続 | ストレス要因がなくなれば改善しやすい | 長期間続きやすい |
| 重症度 | 軽度から中程度 | 重度のケースも多い |
| 治療方法 | 環境調整やカウンセリング | 左記のほか、薬物療法やより高度な心理療法を含む医学的アプローチ |
適応障害の治療は?

適応障害の治療には、以下のような方法があります。
環境調整
適応障害の原因はストレスです。ですから、職場におけるストレスが適応障害を引き起こしていることが判明した場合には、業務の量や内容、職場での人間関係などの負担を軽減し、ストレスを減らすことが重要です。業務内容の調整や配置転換、リモートワークの導入が有効です。
心理療法
カウンセリングや認知行動療法(CBT)が効果的です。ストレスへの対処法を学び、適応力を高めます。
薬物療法
うつ病と違って、適応障害の場合には環境調整や心理療法などで改善します。しかし、重度化してうつ状態や不安感、不眠などの症状が強く現われている場合には、抗不安薬や睡眠導入剤、あるいは抗うつ薬などの薬が処方されることがあります。この点に関しては、医師の判断を仰ぎましょう。
職場側でできる適応障害対策は?

企業や施設・団体が従業員の適応障害を防ぐためにできる対策として、以下の方法が挙げられます。
- ストレスチェックの実施
- メンタルヘルス研修の導入
- 柔軟な勤務体系の整備
- カウンセリング制度の活用
- 定期的な面談
これらの対策を講じることで、従業員のメンタルヘルスを守ることができます。
適応障害の人にはサボり癖がありますか?

適応障害はうつ病と異なり、ストレスの原因から離れると症状が軽くなります。そこで、自身に興味のあることや趣味を楽しむことができます。 個人差はありますが、睡眠や食欲は問題のないケースも少なくありません。
その様子を上司や同僚、あるいは家族が見て、「甘え」や「さぼり癖」などと非難するケースがあります。そうすると、当事者はますますストレスを抱えて適応生姜が悪化してしまいかねません。
非難するのではなく、当事者の話に耳を傾けてつらい気持ちを受容・共感したり、ストレス要因を取り除くための配慮したりするなど、サポートする姿勢を心がけましょう
受講生の感想

Aさん(30代・営業職)
仕事中は無理がきくのですが、帰りの車の中で意味も無く涙が出るようになっていました。研修後に受診したところ、適応障害と診断されたました。上司の理解と主治医によるカウンセリングのおかげで、今は無理なく働けるようになりました。
Bさん(40代・管理職)
メンタルヘルス研修で適応障害について学び、部下への接し方が変わりました。今後も、適切なサポートができるようになりたいです。
Cさん(20代・事務職)
研修後に、ストレスチェックが導入されました。それを受けて早期に異変に気づき相談したことで、症状が悪化する前に対処できました。おかげで休むことなく働き続けられています。
まとめ
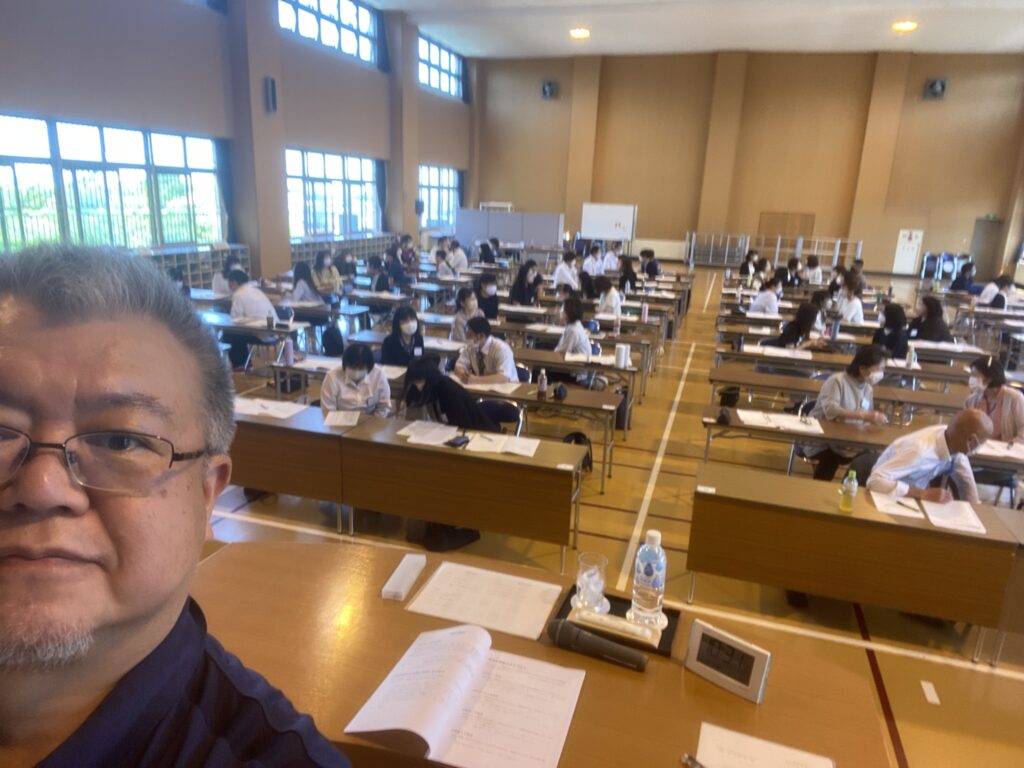
適応障害は誰にでも起こり得るメンタルヘルスの問題です。適切な対処をすることで回復が期待できるため、職場での理解とサポートが不可欠です。本記事で紹介した対策を参考に、職場のメンタルヘルスを整えていきましょう。
私は職場のメンタルヘルスに関する研修を行なっています。メンタル不調の従業員に、上司や同僚がどのように接したらいいかについても、豊富な演習やワークショップを交えながら具体的に指導します。ご興味のある方は、ぜひ公式サイトをご覧ください。お問い合わせも大歓迎です。
→ オアシス・カウンセリング・サービス公式サイト