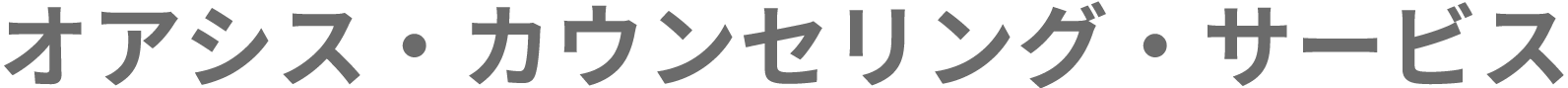「かなり笑った!」アンガーマネジメント研修の内容と感想@福島県須賀川市・郡山市

「アンガーマネジメント」という言葉を聞いて、怒りを取り扱うため堅苦しい研修なのではないかとイメージなさる方も多いのではないでしょうか。私が行なうアンガーマネジメントに関する研修では、笑いあり、気づきありで、多くの企業や団体からご好評いただいております。
この記事では、私が行なっているアンガーマネジメントに関するメンタルヘルス研修の具体的な内容や効果、参加者の声を詳しくご紹介します。
目次
アンガーマネジメントとは?

アンガーマネジメントとは、怒りの感情を上手にコントロールするためのスキルを学ぶことです。 「怒らない」ことを目指すというより、怒りを感じたときに、その怒りを正しく自覚し、正しく表現する方法を学ぶことで、自分自身や周囲の人との関係をより良くしていくことが目的です。
職場においてアンガーマネジメントを意識すると、以下のような効果が期待できます。
- 職場のコミュニケーションが改善される
- 上司も部下もストレスが軽減する
- パワハラ案件が減る
- 生産性が向上する
アンガーマネジメント研修で何を学ぶか

アンガーマネジメント研修では、以下のような内容が取り上げられます。これらの内容を通じて、参加者は自分自身の感情と向き合い、適切に対処することができるようになります。
(1) 怒りのメカニズム
怒りがどのように生じるのか、その背景やトリガーを学びます。
(2) 自己認識の向上
いくつかの怒りのパターン、傾向を紹介し、自分の怒りがどのような特徴を持っているか把握していただきます。自分自身の怒りを客観的に見つめることで、冷静に対処しやすくなります。
(3) 具体的な対処法の習得
怒りを感じた際の具体的な対処法や、冷静さを保つためのテクニックを実践的に学びます。
実際の研修の内容は、各企業の担当者さまとの話し合いによって決定します。
怒りが生じるカラクリ

研修内容を少し紹介します。まずは怒りのメカニズム、怒りがどうして生じるかというカラクリについての解説です。対処法も、このカラクリをベースに紹介しています。
怒りは二次感情
心理学では、「怒りは二次感情である」と言われます。二次感情とは、「2番目に出てくる感情」という意味です。ということは、怒りより前に出てくる一次感情があるということですね。
怒りの前に出てくる一次感情は、相手の言動によって、すなわち相手が何かをしたり、期待していたことをしてくれなかったりしたときに感じる嫌な感情です。悲しみ、痛み、寂しさ、退屈、不安、恐怖、否定的な驚き、疲れなどです。
たとえば、「夫が今年も私の誕生日を忘れて祝ってくれなかった」という出来事が起こったとします。それによって「私は愛されていない」と思った妻は悲しくなるでしょう。すると、そんな悲しみを与えたあの加害者の男には天罰が下るべきだと思います。そして、「もしも天が彼をさばかないのであれば、我がさばく!」「月に代わっておしおきよ!」というわけで出てくるのが怒りです。
怒りは処罰感情
ですから、怒りは自分を嫌な気持ちにさせた相手を処罰するため、復讐するために出てくる特殊な感情です。
そして、怒りを感じた人は相手を攻撃して処罰を実行します。怒鳴って萎縮させたり、暴力を振るって痛い目にあわせたり、泣きわめいて罪責感で苦しめたりするのです。
しかし、怒りを向けられた人はどうでしょうか。怒りは処罰感情なので、まともに受け止めたら傷つきます。
そこで、耳をふさいでその場をやり過ごしたり、その場から逃げ出したりして避けるかも知れません。あるいは傷つけられた復讐のために怒りがわき上がってきて、逆ギレしてくるかも知れません。
いずれにしても、最初に怒った人が「本当に伝えたいこと」は、怒りを向けられた人には伝わらないことがほとんどです。ですから、本当に伝えなければならないことを伝える技術を磨く必要があります。
本当に伝えるべきことを伝える
怒りを怒りのまま伝えても、本当に伝えるべきことは伝わりません。本当に伝えるべき内容は、最低限次の3つです。
- 怒りの元となった一次感情
- 一次感情を感じた理由
- 今後どうしてもらいたいか
これをどのように見つけるか、そして具体的にどのように表現するかについて、私のアンガーマネジメント研修では演習を交えながら学んでいただきます。
アンガーマネジメントにおける自己客観視

アンガーマネジメントにおいて大切なことは、怒っている自分自身を客観視することです。自分を客観的に見つめることができるようになると、冷静に対処することができるようになります。そのための方法も研修で学んでいただきます。
まずは落ち着くための「6秒ルール」
人間が怒りを感じると、体を戦闘態勢にするために血中にアドレナリンが大量に分泌されます。その結果、筋肉に酸素を大量に送り込むため、息が荒くなり、血管が膨らんで顔が紅潮し、好戦的な気分になります。
ところが、実際に戦闘が始まらずに6秒経過すると、アドレナリンの血中濃度が低下し始めます。そして、だんだんと気持ちが落ち着いてくるのです。
自分を客観視したり、適切な対処をしたりするには、冷静な精神状態でなければなりません。そこで、怒りを覚えたら、それを表に出さないで最低6秒間我慢します。具体的には、以下のようなやり方で6秒間をやり過ごしましょう。
- 心の中で、1から6までゆっくり数える
- 6秒間深呼吸する
- 手足を動かしたり、首を回したりして、動いている部分に意識を向ける
- 手のひらに、何に対して怒っているか指で書く
- その場を離れる
怒りを理解するための「4つの軸」
アンガーマネジメントにおいては、怒っている自分について客観的に見つめることができるようにならなければなりません。そこで、4つの軸にしたがって自分の怒りを評価します。その4つの軸とは、「強度」「頻度」「持続性」「攻撃性」です。
- 強度:我を忘れるほど強く怒ってしまわないか
- 頻度:怒ったりイライラしたりすることが多くないか
- 持続性:過去の出来事に対していつまでも怒りを保ち続けていないか
- 攻撃性:相手や第三者、あるいは自分自身を傷つけたり、物に当たったりしないか
これらが強い場合には、本人の心身の健康を損なったり、周りの人たちとの人間関係がおかしくなったりしてしまいます。ですから、怒りを適切にコントロールすることが必要です。
アンガースケール(怒りの数値化)
自分が今感じている怒りに、10点満点で点数をつけます。0点がまったく怒っていない状態で、10点が怒りマックスの状態です。
捉えどころの無い怒りをこのように数値化することで、自分の精神状態や状況を客観視できるようになって落ち着いてくるものです。
感情日記
その日怒りを感じたことについて日記に記録します。その際、怒りを感じた状況、相手、怒りの引き金になった相手の具体的な言動、そして怒りの強さ(上記のアンガースケール参照)について書き出しましょう。
これを続けることで、自分が怒りを感じやすい状況や相手の言動のパターン、そして怒りを表すことで自分が相手に本当は何を伝えたかったのかが見えてきます。
私のアンガーマネジメント研修の特長

笑える研修
研修に笑いが必要だろうか。そんなふうに思われる方もいらっしゃるかも知れません。しかし、笑いはストレスを軽減し、学習効果を高めることがさまざまな調査・研究で証明されています。
そこで、私のメンタルヘルス研修思わずクスッと笑えるような例話を交えることを意識しています。そして、「怒りに関する研修だから、固い内容なのかと思ったら、ずっと笑っていた気がします」「楽しくて、あっという間に終わっていました」という感想をよくいただきます。
科学的なアプローチ
研修では、怒りの感情がどのように生まれるのか、そのメカニズムを分かりやすく解説します。怒りは他の感情とは違う特殊な感情であり、その発生の仕方も独特です。このメカニズムを理解することで、実際に怒りを感じたときに冷静に対応することが可能になります。
具体的なスキルの紹介
私のアンガーマネジメントに関する研修では、単に理論を学ぶだけでなく、参加者が「今日から使える」と思えるスキルを身につけていただくことを重視しています。
参加者主体のワークショップ形式
講義形式だけでなく、参加者が実際に手を動かし、考え、共有する時間を多く設けています。
たとえば、あるワークでは、最近誰かに対して怒りを感じたエピソードについて話し合っていただきました。イライラした過去のエピソードを他の人に話すことで、怒りを感じた人も気持ちが楽になります。
そして、聞く人たちも「自分だけじゃなく、他の人も同じことで悩んでいる」と気づかされ、ホッとします。
まとめ

私は、須賀川市と郡山市を中心に、福島県内や山形・宮城・栃木など近隣県でメンタルヘルス研修を行なっています。その中でもアンガーマネジメントに関する研修は、笑顔と実践的な学びを両立させた内容で、多くの企業・団体・施設の皆様から高い評価をいただいております。
受講なさった方からは、たとえば次のような感想をいただいています。
- アンガーマネジメントに関する研修というと、堅苦しい講義を思い描いていましたが、とても楽しい時間でした。
- 怒ると自分自身の心も疲弊します。うまくコントロールできれば、自分自身のためにもなると感じました。
- 職場だけでなく、家庭などでも使えるスキルを学べて良かったです。
怒りを上手にコントロールできるようになると、従業員間のストレス軽減をもたらすばかりか、やる気を引き出して生産性の向上にもつながります。
社員の福利厚生プログラムの一環として、ぜひ私のメンタルヘルス研修、特にアンガーマネジメントに関する研修をご検討ください。お問い合わせや詳細については、以下の公式サイトからお気軽にご連絡ください。
→ オアシス・カウンセリング・サービス公式サイト