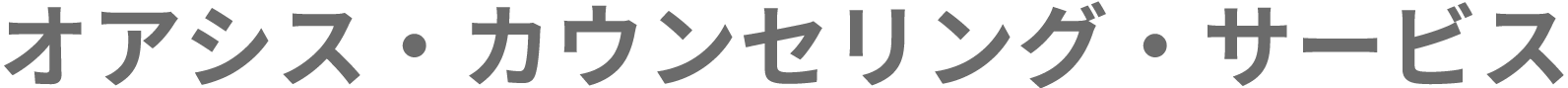メンタルヘルス対策は意味がない? それは誤解です!【須賀川・郡山の医療・福祉事業者様へ】

「うちの職場は人手不足で、辞める人も多い。どうすればいいんだろう…」
そんな悩みを抱えている医療・福祉事業者の方は少なくないのではないでしょうか。特に、人が辞めていく原因について、「どうせ給料が低いから」「仕事が大変だから」と、諦めに近い気持ちを抱いているかもしれません。
そして、「メンタルヘルス対策? そんなことをしても、どうせ離職率は変わらないだろう」と思っていませんか?
もしそう思われているとしたら、それは大きな誤解です!
実は、従業員のメンタルヘルスと離職率の間には、密接な関係があります。そして、メンタルヘルス対策は、皆さんが思っている以上に、離職率改善に効果を発揮する可能性を秘めているのです。
目次
メンタルヘルス対策は「根性論」ではありません

皆さんは「メンタルヘルス対策」と聞くと、どのようなイメージをお持ちでしょうか?
もしかしたら、「個人の気持ちの問題でしょ?」「もっと気を強く持て、で片付く話じゃないの?」と感じるかもしれません。しかし、メンタルヘルス対策は、決して個人の精神力に頼る「根性論」ではありません。
メンタルヘルスとは、心の健康状態全般を指します。そして、職場でいうメンタルヘルス対策とは、従業員がストレスなく、いきいきと働ける環境を整えるための取り組みを指します。
これは、従業員一人ひとりのパフォーマンスを最大化し、ひいては組織全体の生産性向上にも繋がる、極めて現実的な経営戦略の一つなのです。
従業員の「辞めたい」を加速させる見えないストレス
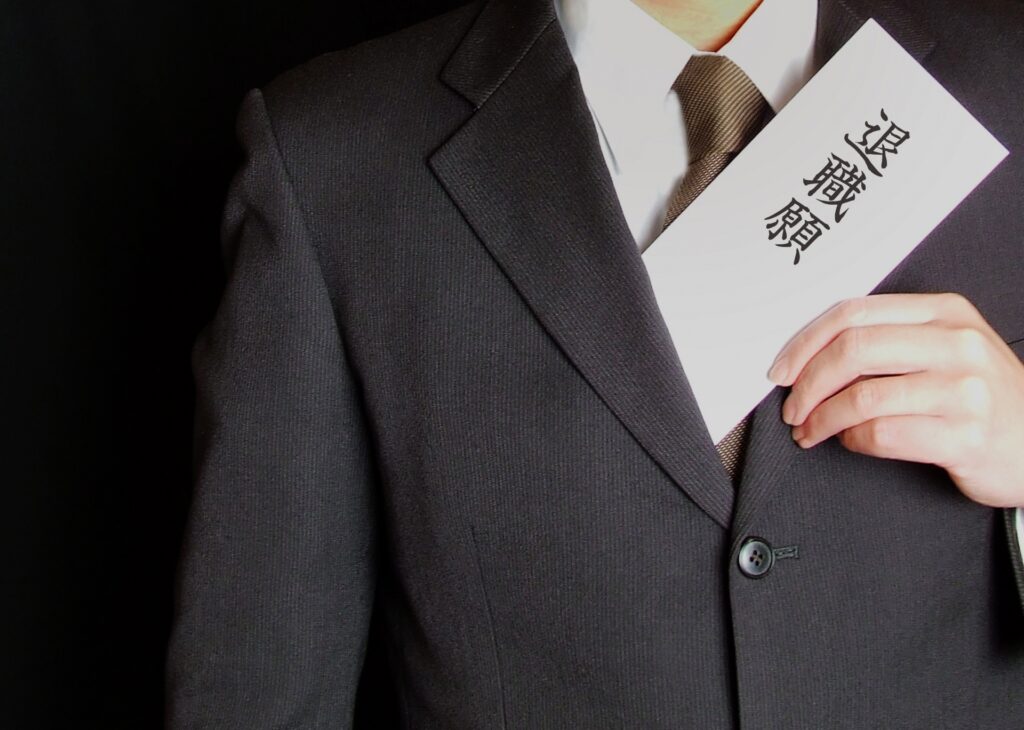
では、なぜメンタルヘルス対策が離職率に影響するのでしょうか? その背景には、従業員が職場で抱える「見えないストレス」が大きく関係しています。
特に医療・福祉の現場は、命や生活に関わる責任の重い仕事であり、精神的な負担が大きいことは皆さんもご存じのとおりです。しかし、そのストレスは単に「忙しい」「疲れる」といった目に見えるものだけではありません。
見えないストレス
「見えないストレス」とは、たとえば、
人間関係の悩み
上司や同僚とのコミュニケーションがうまくいかない、ハラスメントがある、といった問題は、従業員の心に深い傷を与え、職場への不信感へと繋がります。
やりがいの喪失
自分の仕事が評価されない、キャリアアップが見込めないと感じると、モチベーションが低下し、「このままでいいのか?」という疑問を抱き始めます。
不規則な勤務体制や過重労働
医療・福祉の現場では避けられない部分もありますが、慢性的な睡眠不足や疲労は、身体だけでなく心にも大きな負荷をかけます。
患者さんや利用者さん、そのご家族との関係
日々、様々な感情と向き合う中で、心が疲弊してしまうことも少なくありません。
制度やルールの不透明さ
評価制度がわかりにくい、有給が取りにくい雰囲気があるなど、漠然とした不公平感や不安感は、じわじわと従業員の心を蝕みます。
退職の理由は給料だけではない
これらのストレスが積み重なることで、従業員は「この職場で働き続けるのは難しい」と感じるようになります。そして、その感情が頂点に達した時、「辞める」という選択肢が現実味を帯びてくるのです。
「給料が低いから辞める」という理由で退職する方ももちろんいますが、実はその背景には、ストレスからくる「精神的な疲弊」が隠されているケースが少なくありません。
給料が低くても、職場の人間関係が良好で、やりがいを感じられるのであれば、踏みとどまる人はたくさんいます。しかし、ストレスが限界に達すると、たとえ給料が多少良くても、心身の健康を守るために退職を選ぶ、という状況になりかねません。
そして、離職者が増えると残された従業員にしわ寄せが来て、肉体的にも精神的にも疲弊します。その結果、ますます人がやめていくという悪循環に陥りかねません。
メンタルヘルス対策の3つの効果

では、具体的にメンタルヘルス対策が、職場全体に対してどのような良い効果をもたらすのでしょうか。ここでは3つ挙げたいと思います。
(1) ストレスの軽減と心身の健康維持
まず、メンタルヘルス対策の最も直接的な効果は、組織の宝である従業員のストレスを軽減し、心身の健康を維持することです。心身共に健康でなければ、従業員は十分に力を発揮することができません。
(2) 従業員のエンゲージメント向上と定着率アップ
次に、メンタルヘルス対策は、従業員のエンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)を高め、定着率を向上させます。
従業員は、自分たちが大切にされていると感じると、会社への忠誠心が高まります。「この会社は、私たちのことを考えてくれている」と感じることで、仕事へのモチベーションも向上し、結果としてパフォーマンスも上がります。
(3) 採用コストの削減と生産性の向上
最後に、メンタルヘルス対策は、採用コストの削減と生産性の向上という、具体的な経営メリットをもたらします。
離職率が高いと、常に新しい人材を募集し、採用し、育成するコストがかかります。求人広告費、採用担当者の人件費、新人研修費用など、目に見えないコストも膨大です。
しかし、メンタルヘルス対策によって離職率が低下すれば、これらの採用コストを大幅に削減することができます。 既存の熟練したスタッフが長く働き続けてくれることで、業務のノウハウが蓄積され、全体のサービス品質も向上します。
また、心身ともに健康な状態で働く従業員は、集中力や創造性が高く、効率的に業務を進めることができます。これにより、個人の生産性が向上するだけでなく、組織全体の生産性も向上し、結果として医療・福祉サービスの質の向上にも繋がるのです。
今からできる! 離職率を下げるメンタルヘルス対策の第一歩

「でも、具体的に何をすればいいの?」
そう思われた方もいるかもしれません。もちろん、本格的な対策には時間とコストがかかる場合もありますが、まずは今からできる小さな一歩を踏み出すことが大切です。
(1) 従業員の「声」に耳を傾ける
まずは、従業員が何を考え、何に困っているのかを知ることから始めましょう。
定期的な面談の実施
上司と部下が定期的に1対1で話す機会を設けることで、業務上の課題だけでなく、個人的な悩みも打ち明けやすい雰囲気を作ることができます。
アンケートや意見箱の設置
匿名で意見を吸い上げられる仕組みを作ることで、普段言いにくいことも本音で話してくれる可能性があります。
相談窓口の設置
悩みを抱えた時に、安心して相談できる場所があれば、一人で抱え込まずに済み、早期に問題解決に繋がります。
休憩時間などの雑談を重視する
何気ない会話の中から、従業員が抱えている問題やストレスの兆候が見えてくることもあります。
どのような形で話を聞くにせよ、大切なのは「直してやろう、励ましてやろう、教えてやろう」という思いはいったん脇に置いて、まずは相手の話を最後まで聞き、その気持ちに寄り添うことです。
それにより信頼関係が構築され、早期の問題発見に繋がるとともに、さまざまな支援も素直に受け取ってもらいやすくなります。
(2) 感謝とねぎらいと承認の言葉を伝える文化を育む
日々の業務の中で、お互いに感謝の気持ちを伝えたり、ねぎらい合ったりすることは、職場の雰囲気を大きく改善します。
感謝の言葉を積極的に伝える
上司から部下へ、同僚から同僚へ、「ありがとう」「助かったよ」といった言葉を意識的に伝えることで、心理的な安心感が生まれます。カードに感謝の言葉を書いて渡すのも良い方法です。
ねぎらいの言葉をかける
がんばっている部下や同僚に対して「ご苦労さま」「暑い中、大変でしたね」「今日もお互いがんばりましたね!」と、積極的にねぎらいの声かけをしましょう。
望ましい行いを評価する
小さなことでも、従業員の努力や望ましい行いを具体的に認めることで、モチベーション向上に繋がります。
大切な心構えは、相手の行動を「当たり前」だと思わないこと。むしろやって当然のことを拾って、感謝したりねぎらったり認めたりしましょう。

(3) その他、できることをやる
その他、次のような取り組みが効果的です。
ストレスチェックの実施とフィードバック
従業員のストレスチェックが、中小企業でも義務化されようとしています。ストレスチェックの主な目的は、従業員が自分のストレス状態を客観的に把握することです。それにより、早めに適切な対処をとることができます。
また、組織としても従業員全体のストレス状況を把握し、対策を講じるきっかけになります。積極的に導入・活用しましょう。
休憩時間の確保や労働時間管理の徹底
十分な休憩や休息は、身体だけでなく心の疲労回復にも不可欠です。適切な労働時間管理は、過労による心身の不調を防ぎます。
ハラスメント対策の徹底
ハラスメントは従業員の尊厳を傷つけ、精神的なダメージを大きく与えます。毅然とした態度でハラスメントを許さない職場環境を築くことは、安心感に繋がります。
これらの対策は、従業員が心身ともに健康な状態で働くことをサポートし、結果的に「もう無理だ」と感じる前に離職を防ぐことに繋がります。
従業員の意見を吸い上げる機会の創出
定期的な面談やアンケートなどを通じて、従業員の声に耳を傾ける姿勢を示すことで、彼らは「自分たちの意見が尊重されている」と感じます。
適切なフィードバックと成長機会の提供
従業員の努力を認め、具体的なフィードバックを与えることは、彼らの自己肯定感を高め、成長を促します。また、スキルアップやキャリア形成の機会を提供することは、将来への希望を与え、長期的なキャリアを考えるきっかけになります。
働きやすい職場環境の整備
快適な休憩スペース、きれいなロッカールーム、働きやすい動線など、物理的な環境整備も、従業員の満足度を高める要因となります。
専門家によるメンタルヘルス研修
メンタルヘルスに関する専門家、離職率低下策に関する専門家を交えて、経営者や上司向け、あるいは従業員向けの社内研修を行なうのも良い方法です。
このような取り組みは、従業員が「この職場で働き続けたい」と強く思うきっかけとなり、結果として離職率の低下に繋がります。
メンタルヘルス対策は「未来への投資」です

「メンタルヘルス対策なんて、うちには関係ない」「やっても意味がない」
もし、今もそう思われているのであれば、もう一度考えてみてください。
従業員のメンタルヘルスは、個人の問題ではありません。それは、皆さんの職場の生産性、サービスの質、そして未来に直結する重要な経営課題です。
メンタルヘルス対策は、決して「特別なこと」ではありません。従業員が安心して、気持ちよく働ける環境を整えること。それは、従業員の離職を防ぎ、優秀な人材を定着させ、ひいては組織全体の成長に繋がる、未来への賢い投資なのです。
「人手不足で、もう限界だ…」そう嘆く前に、ぜひ一歩踏み出して、従業員のメンタルヘルスに目を向けてみませんか? その小さな一歩が、きっと皆さんの職場を、そして医療・福祉業界全体を、より良い方向へと変えていくはずです。

離職率を下げるメンタルヘルス研修
私たちオアシス・カウンセリング・サービスでは、特に医療・福祉事業所様のメンタルヘルスに関する社内研修に講師を派遣しています。
1. 経営者・上司向けの研修
- 部下のストレスを軽くし、離職率を下げる方策
- 部下の本音を引き出す話の聞き方
- やる気を引き出す伝え方
- パワハラにならない指導法
- 怒りのコントロール法
2. 従業員向けの研修
- ストレス解消法
- ストレスに負けない強い心の育て方
- 上司とのコミュニケーション
- 利用者さんやその家族とのコミュニケーション
- 効果的な目標の立て方
- 高慢さとは異なる本当の自信の付け方
以上は研修内容の例です。実際の内容は、事前に担当者様と話し合いの上決定します。
さらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下のサイトから資料をご請求ください。
→ オアシス・カウンセリング・サービス公式サイト