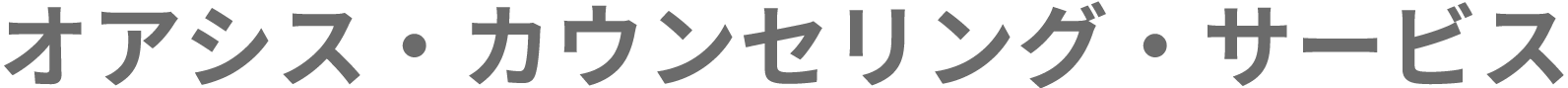心理的安全性の高め方【辞めない職場作り】須賀川・郡山の医療・福祉事業所

人材の定着は、現代の企業・団体・施設にとって喫緊の課題です。特に、職場での人間関係やメンタルヘルスの問題が離職の大きな要因となっている今、注目されているのが「心理的安全性」です。これは、従業員が自分らしく働け、意見を自由に言える環境を指します。本記事では、心理的安全性を高めるための具体的なノウハウと、実際に取り組んだ現場での感想をご紹介します。
目次
心理的安全性とは何か? 職場への影響

「心理的安全性(Psychological Safety)」とは、チームやグループの中で自分の考え・感情・意見などを率直に表現しても、否定や非難を恐れずに済む状態を指します。
この概念は、ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授によって提唱され、Googleの「プロジェクト・アリストテレス」でも生産性の高いチームに共通する要素として確認されました。
心理的安全性が高い職場では、次のような効果が期待されます。
- 離職率の低下
- 創造性・アイデアの向上
- チーム間の連携強化
- メンタル不調の予防
一方で、心理的安全性が低いと、従業員はミスを隠し、意見を控えるようになり、結果として職場に閉塞感が生まれます。
何も指導しないことではない
ただし、心理的安全性が高い職場というのは、部下がミスを犯したり、意見や行動に不備があったりした際に何も指摘や指導をしないことではありません。
相手の人間性や能力を否定したり、皆の前で罵倒して恥をかかせたり、攻撃的な言い方をしたりせず、具体的に不適切な「行動」を指摘し、望ましい「行動」を具体的に求める指導をするのです。
✅ 留意すべきポイント:
- 性格や能力を問題にしないこと
- 相手の自尊心に配慮すること
- 指摘したり改善を求めたりする際に、具体的な行動を示すこと
たとえば、書類に誤字が多い部下に対して上司が指導する場合、どちらの言い方が心理的安全性を担保し、やる気を損なわずに済みそうでしょうか?
- 「また誤字がある。本当に君は注意力が散漫だなぁ。もういい加減にしてくれ!」
- 「ここの”御社”が”恩社”になっているよ。提出前に、必ずプリントアウトして2度は読み直すようにしよう」
メンタルヘルスと心理的安全性の関係

心理的安全性は、メンタルヘルスの土台となる環境とも関係があります。心理的安全性が高まって職場での不安感や孤立感が軽減されると、従業員はストレスを溜めにくくなり、うつ病や燃え尽きの予防につながります。ひいては、離職率の低下にも効果的です。
厚生労働省の調査でも、精神的健康の維持には「人間関係の質」が大きく影響していることが報告されています。メンタル不調が深刻化する前に、心理的安全性を高めることは、組織全体の健全性にも直結します。
心理的安全性を高める4つの具体策

(1) 上司・リーダーによる「受容と傾聴」の姿勢
リーダーがどれだけ部下の話に耳を傾けているかは、職場の心理的安全性に直結します。受容・傾聴するとは、意見の内容や態度に同意することではありません。途中でさえぎらずに最後まで聴ききることです。
✅ 実践ポイント:
- 会議中に部下の発言を遮らない
- 提案に対して「それは面白い視点ですね」と反応する
- 失敗しても、「挑戦したことを評価している」と伝える
ポジティブなフィードバック
ポジティブ・フィードバック(良い点を具体的に伝えること)は、従業員の安心感を育みます。批判だけでなく、日頃の貢献や成長に目を向けることが大切です。
✅ 実践ポイント:
- 月に1回の1on1ミーティングで個別に感謝を伝える
- 「〇〇さんの◯◯の対応が助かりました」「訪問先での掃除がていねいだと、利用者さんたちから感謝の言葉をいただいています」など具体的に望ましい点を指摘する
- チーム全体で良い行動をシェアする(特定のメンバーだけが賞賛されるのではなく、すべてのメンバーが、何かしら良い行動をフィードバックされるようにすること)
(3) 自分も「不完全な存在」であることを示す
リーダーが完璧を演じようとすると、部下も弱みを見せづらくなります。心理的安全性の高い職場では、上司自身が「分からない」「ミスした」と正直に話したり、部下に助けを求めたりすることで、自然と部下も心を開けるようになります。
✅ 実践ポイント:
- ミスや戸惑いを正直に共有する
- 部下に相談したり、頼ったりする
- 自分自身が学び続けている姿勢を見せる
- 上意下達ではなく、「一緒に考えましょう」という対話型の姿勢をとる
(4) チームで価値観や目標を共有する
共通のビジョンや目的を持つことは、相互信頼を高める土台になります。特に、目の前の仕事の意味や「なぜそれを行うのか」を全員で共有すると、協力や助け合いが生まれやすくなります。
✅ 実践ポイント:
- 月1回のミーティングで業務の目的や理念を確認する
- 各メンバーの強み・得意分野を紹介し合う
- 共通目標を可視化し、進捗をチームで確認する
- すべてのメンバーが重要な役割を負っているということを確認する
心理的安全性向上セミナー受講者の声

実際に心理的安全性の向上に取り組んだ受講者の方々から、以下のような声が寄せられています。
🔹 社会福祉法人施設長(50代・男性)
「これまで部下に対して厳しく接することが多く、距離ができていましたが、研修で“傾聴”の大切さに気づきました。今では自然と職員が話しかけてくれるようになり、職場の空気がやわらぎました。」
🔹 医療法人・看護師長(40代・女性)
「スタッフが失敗を報告してくれないことに悩んでいましたが、自分自身の姿勢が原因だったと気づきました。ポジティブ・フィードバックを心がけるようにしたり、自分自身の弱さを見せたりするようにしたところ、少しずつ本音が出るようになり、看護の質も向上しています。」
🔹 一般企業・人事担当(30代・男性)
「心理的安全性の大切さは知っていたつもりでしたが、研修で“どう実践するか”まで学べたのが良かったです。チームでのフィードバック共有が活発になり、離職も明らかに減少しています。」
まとめ

心理的安全性は、単なる「話しやすい雰囲気」を超えた、職場の健全性と生産性の根幹にかかわるテーマです。上司の姿勢、日常的なフィードバック、価値観の共有といった小さな取り組みの積み重ねが、従業員の定着・成長・メンタルヘルスにつながります。
離職率の高止まりや人材不足に悩む職場こそ、まずは「心理的安全性」に目を向けてみませんか? 人が辞めない、むしろ「ここで働き続けたい」と思える環境づくりは実現可能です。

私たちオアシス・カウンセリング・サービスでは、事業主さまや各部門のリーダーの方向けに、心理的安全性を高めるための社内研修に講師を派遣しています。興味のある方は、ぜひ私どもの公式サイトをご覧ください。
→ オアシス・カウンセリング・サービス公式サイト