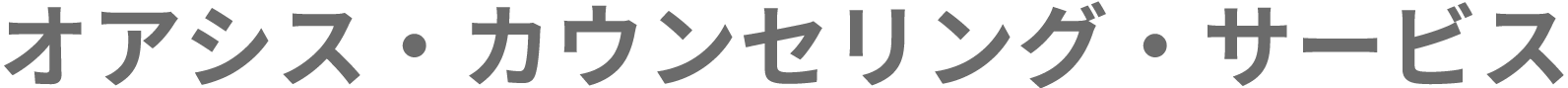従業員の「静かな退職」をどう防止し対処するか

現代の企業経営において、従業員のエンゲージメント(企業に対して持つ愛着心や貢献意欲、会社への信頼や一体感など)と定着は、持続的な成長を実現するための不可欠な要素となっています。
しかし近年、「静かな退職」という現象が注目を集めています。これは、従業員が表面上は通常通り業務を遂行しながらも、仕事への情熱や貢献意欲を失い、最小限の努力しかしなくなる状態を指します。
このような状況は、組織全体の生産性低下や士気の低下を招くだけでなく、優秀な人材の流出リスクを高める深刻な問題です。
本記事では、この「静かな退職」の兆候を早期に察知し、未然に防ぐための具体的な対策と、既に兆候が見られる従業員への効果的な対処法について、メンタルヘルスの専門家の視点から詳しく解説してまいります。
目次
「静かな退職」とは何か?

「静かな退職」とは、従業員が与えられた業務はこなすものの、それ以上の努力をせず、昇進やキャリアアップへの意欲も失い、心理的な距離を置いた状態で働くことを指します。
「静かな退職」では実際に退職するわけではないため、表面上は問題がないように見えることが多い点が特徴です。しかし、内面では仕事に対する熱意が失われ、与えられた職務範囲を最低限でこなすに留まるため、企業の生産性や創造性を阻害する要因となります。
それに加えて、「静かな退職」状態が続くと、
- やがて本人が本当に離職してしまう。
- 他の従業員の負担が増えることで、新たな離職者を生んでしまう。
といった問題が起こってくるでしょう。
「静かな退職」の原因

従業員が「静かな退職」の状態に陥る原因には、いくつかの要因が考えられます。
一つは、コロナ禍を経て働き方が大きく変化し、ワークライフバランスの重要性が再認識されたことです。過度な労働やストレスに対する反動として、仕事に全てを捧げるのではなく、自身の生活や心身の健康を優先したいという意識が高まりました。
また、労働環境や人間関係の悪化、自身の貢献が正当に評価されないという不満、キャリアパスの不透明さなども、従業員が「静かな退職」を選ぶ大きな理由となり得ます。
まとめると、
(1) キャリアパスの不透明さ
若手もベテランも、自分のキャリアに展望がない場合に「どうせ頑張っても変わらない」と無気力に陥ってしまいます。
(2) 心理的安全性の不足
職場に安心して発言したりチャレンジしたりできる文化がなく、失敗したり下手なことを言ったりしたら責められるという恐れが蔓延している場合、従業員はチャレンジしない方が安全だという後ろ向きの気持ちになります。
(3) 負担の偏り
積極的に働く従業員にばかり仕事が集中して負荷が重くなると、不満が蓄積して「真面目に働くと損をする」という気持ちになってしまいます。
(4) ワークライフバランスの難しさ
私生活上の楽しみ、家族との触れ合い、家事や育児との両立に苦難を抱えると、私生活の方を優先しようとして仕事への取り組みが適当になります。
「静かな退職」の徴候

「静かな退職」の兆候は、以下のような形で現れることが多いです。
(1) 業務への意欲低下
新しい仕事や役割に積極的でなくなり、現状維持を求める傾向が強まります。
(2) コミュニケーションの減少
同僚や上司との会話が減り、必要最低限の業務連絡に留まるようになります。会議での発言も少なくなることがあります。
(3) 責任感の希薄化
自分の担当範囲以外の業務には関心を示さなくなり、問題が発生しても自主的に解決しようとしない姿勢が見られます。
(4) 学習意欲の減退
スキルアップや知識習得のための自己投資をしなくなり、キャリアに関する目標が見えにくくなります。
(5) 遅刻や欠勤の増加
頻繁ではないにしても、以前に比べて遅刻や欠勤が増える、あるいは有給休暇を消化することに抵抗がなくなる、といった変化が見られることがあります。
(6) 表情や態度の変化
以前よりも表情が乏しくなったり、覇気がなくなったり、疲れた様子を見せることが増えるかもしれません。
これらの兆候は、単独で現れることもあれば、複数同時に見られることもあります。特に、以前は積極的に業務に取り組んでいた従業員にこのような変化が見られた場合、注意深く観察し、早期に対応を検討することが重要です。
「静かな退職」を未然に防ぐための組織的アプローチ
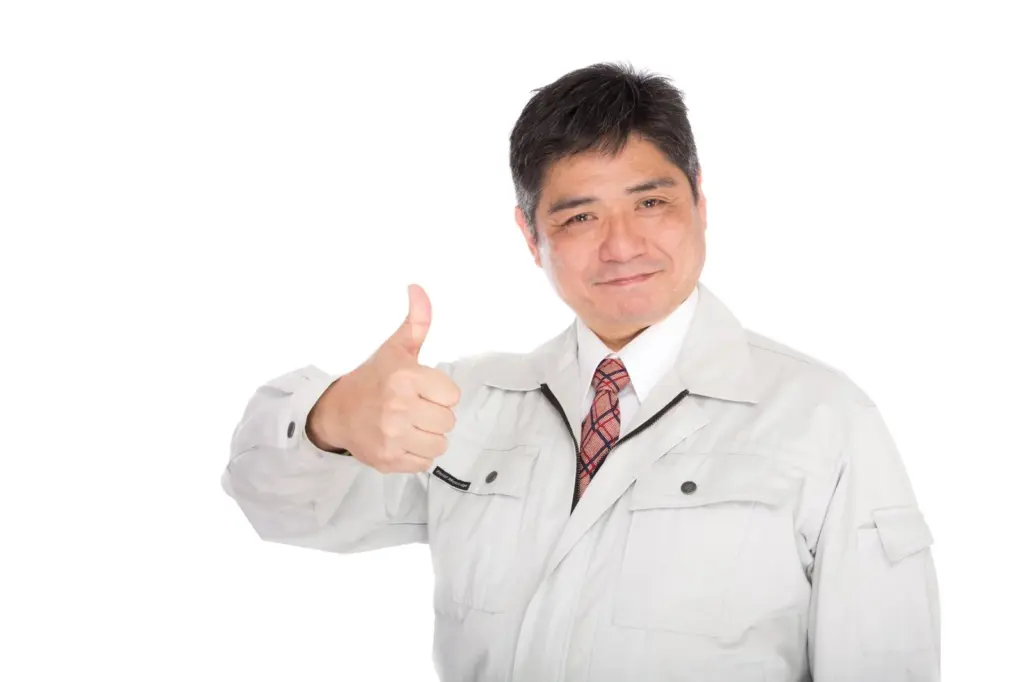
「静かな退職」は、従業員個人の問題として捉えられがちですが、実際には組織全体の環境や文化が大きく影響しています。そのため、未然に防ぐためには、組織的なアプローチが不可欠です。
(1) 明確な評価制度とフィードバックの強化
従業員が「静かな退職」を選ぶ理由の一つに、自身の貢献が正当に評価されていないと感じることが挙げられます。
この問題を解消するためには、明確で透明性の高い評価制度を構築することが重要です。
目標設定は「SMART原則」に基づき具体的に行い、その達成度を定期的に確認します。SMART原則に基づいた目標設定法については、以下の記事をご参照ください。
さらに、定期的な「1on1ミーティング」を通じて、上司から部下へのフィードバックを積極的に行いましょう。単に評価を伝えるだけでなく、良い点は具体的に褒め、改善点については具体的なアドバイスを提供します。そして、部下の意見や提案にも真摯に耳を傾け、双方向のコミュニケーションを心がけることが大切です。
これにより、従業員は自身の仕事が組織にどのように貢献しているかを理解し、モチベーションを維持することができます。
(2) ワークライフバランスの推進と柔軟な働き方の導入
過度な長時間労働やプライベートの時間が確保できない状況は、従業員の心身に大きな負担をかけ、「静かな退職」に繋がる大きな要因となります。ワークライフバランスを推進することは、従業員が仕事と私生活の調和を図り、健全な状態で働き続けるために不可欠です。
具体的には、
- フレックスタイム制度の導入
- リモートワークの導入
- 有給休暇の取得促進
- 残業時間の削減目標の設定
などが挙げられます。
これらの施策は、従業員が自身のライフスタイルに合わせて働き方を選択できる柔軟性を提供し、ストレスを軽減します。
たとえば、育児や介護と仕事を両立させる従業員にとっては、柔軟な働き方が離職を防ぐ重要な要素となります。企業が従業員の生活を尊重する姿勢を示すことで、従業員は組織へのエンゲージメントを高め、自律的に業務に取り組むようになります。
もちろん、目標を立てるだけでなく、それぞれの目標を達成できるような計画を立案して実行する必要があります。
例を挙げると、残業時間の削減目標を打ち出すだけだとサービス残業や持ち帰り業務を増やすだけで、かえって従業員の不満を増大させてしまうでしょう。残業しなくてもよいように、業務内容や業務量を調整したり、従業員の数を増やしたりといった具体的な行動計画の立案と実施が必要です。
(3) キャリア開発支援と成長機会の提供
従業員が自身の成長やキャリアパス(特定の地位や職務に就くために必要とされる経験・スキル・資格などのこと)を見失うと、仕事への意欲を失いやすくなります。これを防ぐためには、キャリア開発支援を積極的に行い、多様な成長機会を提供することが重要です。
具体的には、
- 定期的なキャリア面談の実施
- 社内研修プログラムの充実
- 外部セミナーへの参加支援
- 資格取得支援
などが挙げられます。
従業員が自身のスキルアップや新たな知識の習得を通じて、将来のキャリアビジョンを描けるようサポートすることで、仕事へのモチベーションを維持し、組織への貢献意欲を高めることができます。
また、ジョブローテーションや部署異動など、新しい挑戦の機会を提供することも、従業員の視野を広げ、マンネリ化を防ぐ上で有効です。
(4) 心理的安全性のある職場環境の醸成
従業員が安心して意見を言えたり、失敗を恐れずに挑戦できる心理的安全性の高い職場環境は、「静かな退職」を防ぐ上で非常に重要です。意見が通りにくい、上司や同僚からのハラスメントがある、といった環境では、従業員は自らを発信することを控え、与えられた業務だけをこなすようになります。
心理的安全性を高めるためには、以下のような取り組みが有効です。
- オープンなコミュニケーションの促進
上司と部下、同僚間の活発な意見交換を奨励し、異なる意見も尊重する文化を育みます。 - ハラスメント対策の徹底
ハラスメントに対する明確な方針を定め、相談窓口の設置や再発防止策を講じることで、従業員が安心して働ける環境を保証します。 - 失敗を許容する文化
新しい挑戦に伴う失敗を責めるのではなく、学びの機会として捉える文化を醸成します。これにより、従業員は積極的に行動するようになります。
このような環境を整えることで、従業員は自身の能力を最大限に発揮し、組織への貢献意欲を高めることができます。
既に「静かな退職」の兆候が見られる従業員への対処法

もし既に「静かな退職」の兆候が見られる従業員がいる場合、早期に適切な対処を行うことが重要です。放置すれば、その従業員のモチベーション低下がさらに進行し、周囲の従業員にも悪影響を及ぼす可能性があります。
(1) 個別面談を通じた状況把握と傾聴
最初に行うべきは、対象の従業員との個別面談です。この面談は、決して評価や叱責の場ではなく、従業員の抱える問題や不満、心境を理解するためのものです。もしかしたら、業務内容のミスマッチ、人間関係の悩み、あるいはプライベートな問題が影響している可能性もあります。
上司は、従業員が話しやすい雰囲気を作り、じっくりと傾聴する姿勢が求められます。
面談では、「最近、何か困っていることはありませんか?」「仕事で負担に感じていることはありますか?」など、具体的な質問を投げかけ、従業員が自由に話せるように促します。決して決めつけたり、安易なアドバイスをしたりせず、共感的な態度で耳を傾けることが大切です。
この段階で、従業員が「自分のことを理解しようとしてくれている」と感じられるかどうかが、今後の関係構築において非常に重要になります。
「直そうとするな、分かろうとせよ」(心理学者カール・ロジャース)
(2) 業務内容や役割の見直し
個別面談を通じて従業員の状況が把握できたら、必要に応じて業務内容や役割の見直しを検討します。もしかすると、従業員が現在の業務にやりがいを感じていなかったり、能力が十分に活かされていないと感じているのかもしれません。
例えば、より責任のある業務を任せることでモチベーションが向上するケースもあれば、逆に業務量が多すぎて負担になっている可能性もあります。本人の希望や適性を考慮し、業務の再配分や新しいプロジェクトへの参加を促すなど、柔軟に対応することが求められます。また、キャリアパスの再確認を行い、将来的な展望を共有することで、再び目標を持って業務に取り組めるようになることもあります。
(3) 専門家への相談とサポート
従業員の「静かな退職」の背景には、メンタルヘルスの問題が潜んでいる可能性も考えられます。もし、従業員の言動や態度から精神的な不調が疑われる場合や、組織内での対応が難しいと感じる場合は、外部の専門家への相談を検討することが重要です。
たとえば、産業医や臨床心理士、カウンセラーといったメンタルヘルスの専門家は、従業員の心身の状態を適切に評価し、適切なサポートを提供することができます。
企業としては、従業員が安心して専門家のサポートを受けられるよう、EAP(従業員支援プログラム)の導入や、外部の相談窓口の紹介などを行うと良いでしょう。従業員本人だけでなく、対応に悩む上司や人事担当者も専門家に相談することで、より適切な支援策を講じることが可能になります。
従業員が孤立することなく、必要な支援を受けられる環境を整えることが、早期回復に繋がります。
(4) 再びエンゲージメントを高めるための取り組み
一時的に「静かな退職」状態にあった従業員が、再び仕事へのエンゲージメントを高めるためには、具体的な取り組みが必要です。
たとえば、成功体験を積ませるために、達成可能な目標を設定し、それをクリアした際には具体的な称賛と評価を与えます。また、チームの一員としての貢献を実感できるような役割を与えたり、他の従業員との交流を促進する場を設けることも有効です。
従業員が「自分は組織にとって必要な存在である」と感じられるような機会を提供し続けることで、徐々に仕事への意欲を取り戻していくでしょう。この過程では、焦らず、継続的なサポートが求められます。
メンタルヘルス研修がもたらす効果

従業員の「静かな退職」への対策として、組織的なアプローチや個別対応が重要であることを述べました。これらの取り組みをより効果的に進めるためには、従業員一人ひとりが自身のメンタルヘルスに意識を向け、適切な対処法を学ぶ機会を提供することが不可欠です。そこで、メンタルヘルス研修が非常に重要な役割を担います。
メンタルヘルス研修は、単に知識を提供するだけでなく、ストレスマネジメントの具体的な方法や、コミュニケーションスキルの向上、レジリエンス(精神的回復力)の強化など、実践的なスキルを習得できる場です。管理職向けには、部下の異変に気づくポイントや、声かけの方法、ハラスメント防止策など、より具体的なマネジメントスキルに焦点を当てた内容を提供します。
従業員一人ひとりがストレスに対処する力を養うことで、心身の不調を未然に防ぎ、結果として「静かな退職」の発生を抑制することに繋がります。
受講者の声

私どもオアシス・カウンセリング・サービスの研修を受講された皆様からは、以下のような感想をいただいています。
A社 人事担当者様
従業員のメンタルヘルス対策は喫緊の課題だと感じていましたが、何から手をつければ良いのか悩んでいました。こちらの研修では、『静かな退職』の具体的な兆候から、具体的な声かけの方法、そして組織として取り組むべきことまで、体系的に学ぶことができました。
特に、ワークショップ形式で実践的なロールプレイングができたことで、現場での対応に自信を持つことができました。研修後、実際にいくつかの事例で早期に対応でき、大きな問題になる前に解決できたと実感しています。
B病院 看護師長様
多忙な医療現場では、ストレスを抱え込むスタッフも少なくありません。以前は、どのようにサポートすれば良いか分からず、見て見ぬふりをしてしまうこともありました。
今回の研修で、ストレスチェックの重要性や、チーム内で支え合うことの意義、そして何よりも自分自身のストレスケアの重要性を再認識しました。研修後は、スタッフとのコミュニケーションの質が向上し、お互いの状況を理解し合えるチームになってきたと感じています。離職率の改善にも繋がることを期待しています。
C市町村役場 部署課長様
公務員という立場上、精神的な負担を感じやすい職員も多く、職員のメンタルヘルス対策は重要な課題です。今回の研修は、管理職としてどのように部下の心の健康を守っていくか、具体的なアプローチを学ぶ良い機会となりました。
特に、多様な価値観を持つ部下への対応方法や、ハラスメントにならないコミュニケーションの取り方など、実践的な内容が多く、すぐに職場に活かせるものばかりでした。研修で学んだことを活かし、心理的安全性の高い職場環境づくりに努めてまいります。
これらの声は、メンタルヘルス研修が単なる知識の教授に留まらず、参加者の行動変容を促し、組織全体のウェルネス向上に貢献していることを示しています。従業員が心身ともに健康で、意欲的に働ける環境を整えることは、企業の成長に直結します。
まとめ

従業員の「静かな退職」は、現代社会において多くの企業が直面している深刻な課題です。しかし、その兆候を早期に察知し、適切な対策を講じることで、未然に防ぎ、あるいは既に発生している問題に対処することは十分に可能です。
本記事でご紹介したように、明確な評価制度、ワークライフバランスの推進、キャリア開発支援、そして心理的安全性のある職場環境の醸成といった組織的なアプローチが、従業員のエンゲージメントを高める上で不可欠です。
そして、もし既に「静かな退職」の兆候が見られる従業員がいる場合は、個別面談を通じた丁寧な傾聴、業務内容や役割の見直し、そして必要に応じた専門家への相談とサポートが有効な対処法となります。
これら一連の取り組みの根底には、従業員の心身の健康を守り、彼らが安心して最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を提供するという企業・団体・施設側の強い意思が求められます。
従業員一人ひとりが生き生きと働き、組織全体が活気に満ち溢れるためには、継続的なメンタルヘルス対策が不可欠です。

私どもオアシス・カウンセリング・サービスでは、福島県須賀川市、郡山市をはじめ、福島県内および近隣県の企業・団体・施設の皆様に向けて、貴社のニーズに合わせたオーダーメイドのメンタルヘルス研修を提供しております。
特に最近は、「離職率を下げるための方策」についてお話しする機会が増えています。
従業員の心の健康をサポートし、「静かな退職」を防止する実践的なプログラムにご興味がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。貴社の持続的な成長と、従業員のウェルネス向上に貢献できるよう、全力でサポートさせていただきます。
私どもの研修にご興味のある方は、ぜひ以下の公式サイトをご覧ください。
→ オアシス・カウンセリング・サービス公式サイト