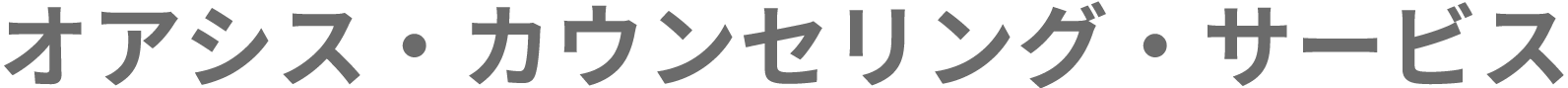反省を成長の糧にする指導法【メンタルヘルス研修@須賀川・郡山】

職場で部下が失敗や不適切な行動をしたとき、上司としてどう反省を促し指導すればよいか、悩む方は多いのではないでしょうか。「反省しなさい」とただ伝えたり失敗を責めたりするだけでは部下の成長にはつながりませんし、指導の仕方を間違えればパワーハラスメントと受け取られるリスクもあります。
しかし、失敗を単なる「後悔」で終わらせず、次につながる「学び」に変えることができれば、部下は大きく成長します。それは、上司の指導の仕方にかかっているのです。
この記事では、部下が失敗したとき、相手を委縮させたり、パワハラ認定されたり、言い訳ばかりで変化が見られなかったりすることなく、自律的な反省を促して成長につなげるための具体的な方法を、3つのステップに分けてお伝えします。
目次
効果的な反省【ステップ1】感情に寄り添い、安全な対話の場を作る

部下が失敗した直後、上司がすべきことは「責めること」ではありません。まずは、彼らが抱えているであろう、不安や後悔、時には反発心といった感情に寄り添い、安心して話せる雰囲気を作ることです。
1-1. まず「聴く」姿勢を持つ
失敗をした部下は、すでに自分自身を責めていることがほとんどです。そこに上司から厳しい言葉が飛んでくると、部下は心を閉ざし、本当の原因や背景を話せなくなってしまいます。
まずは、「何があったか聞かせてもらえるかな?」「話せる範囲でいいから教えてくれる?」といった言葉で、部下が話しやすい雰囲気を作りましょう。このとき、途中で相手の言葉を遮ったり「それは違う」と否定したりせず、一通り最後まで静かに聴くことが重要です。
部下は、自分の話が聞いてもらえたと感じることで、「自分は責められているのではない」「この上司は、自分を理解しようとしてくれている」と安心感を持ち、正直な気持ちを話せるようになります。これは、信頼関係を築く上で欠かせない最初の一歩です。
1-2. 失敗を「個人の資質」ではなく「事象」として捉える
「なんでこんなこともできないんだ」「いつも同じミスをする」といった言葉は、部下の人格や能力を否定していると受け取られかねません。このような言葉は、パワーハラスメントと判断される可能性もあり、注意が必要です。
そうではなく、失敗を「特定の状況で起きた事象」として客観的に捉えましょう。
- 悪い例:「君はいつも詰めが甘いから、こんなミスをするんだ。」
- 良い例:「今回の件は、確認手順に問題があったかもしれないね。確認がおろそかになったのには、どんな原因があったと思う?」
このように、「誰がどれだけ悪いか」ではなく、「なぜその事象が起きたのか」という視点で対話を進めることで、部下は個人攻撃されていると感じることなく、冷静に原因を探り出し、今後同じ失敗をしないための方法を考えることができます。
【効果的な反省ステップ2】原因を深掘りし、客観的な分析を促す

部下の話を聞き、落ち着いた雰囲気で話ができるようになったら、次は失敗の根本原因を一緒に探っていきます。このステップでは、上司が一方的に答えを与えるのではなく、部下自身に考えさせることがポイントです。
2-1. 4W1Hで事実を整理する
感情や主観が入り混じった状態では、適切な反省はできません。まずは事実を整理するために、以下の項目を部下と一緒に確認していきましょう。
- When(いつ): 失敗はいつ起きたのか?
- Where(どこで): どの場所で起きたのか?
- Who(誰が): 誰が関わっていたのか?
- What(何を): 具体的に何が起きたのか?
- How(どのように): どのような状況だったのか?
このプロセスを通じて、部下は漠然とした失敗を具体的な事象として捉え直すことができます。
たとえば、「必要事項報告が遅れた結果、他の社員に迷惑がかかった」という失敗に対し、
「誰に対して、何を、いつまでに報告すべきだったのか」
「最終的に報告したのはいつだったのか」
「報告が遅れた結果、誰に対して、どんな迷惑を与えたのか」
といった問いかけをすることで、起こった出来事を客観的に整理します。
2-2. 根本原因を掘り下げる「なぜなぜ分析」
次に、その事象が起こった原因(Why)を明らかにします。
ここでは、トヨタで用いられている原因究明手法でである「なぜなぜ分析」を紹介します。「なぜなぜ分析」とは、一つの事象に対して「なぜ?」を5回程度繰り返すことで、表面的な原因のさらに奥にある根本原因を突き止めるものです。
例:「お客様へのメール送信ミス」という失敗
- なぜ、メール送信をミスしたの?
→ 確認を怠ったから。 - なぜ、確認を怠ったの?
→ 業者が早く返信を求めていたので、焦っていたから。 - なぜ、焦っていたの?
→ 納期がギリギリで、時間的な余裕がなかったから。 - なぜ、納期がギリギリだったの?
→ スケジュール管理がうまくいっていなかったから。 - なぜ、スケジュール管理がうまくいっていなかったの?
→ 複数の案件が重なり、全体の進捗状況を把握できていなかったから。
このように、表面的な「確認ミス」という原因から、より根本的な「スケジュール管理」という課題が見えてきます。この課題は、部下個人の問題だけでなく、チームや組織全体の仕組みに原因がある可能性も示唆しています。
2-3. 「尋問」にならないよう注意
「なぜ」「どうして」という理由を尋ねる質問は、ともすれば部下に精神的な圧迫を与える「尋問」や「取り調べ」だと感じさせかねません。それでは部下は心をガードし、客観的な振り返りができなくなります。
上司が部下と一緒に「なぜなぜ分析」を行なう際は、「尋問」や「犯人捜し」ではなく、「改善点の発見」という目的で行うことが重要です。そして、極力穏やかな表情や話し方に努めましょう。
【効果的な反省ステップ3】未来に向けた行動計画を立て、実行をサポートする

反省の最終ステップは、得られた学びを具体的な行動に落とし込むことです。「次は気をつけます」という言葉で終わらせないように、上司が部下を導く必要があります。
3-1. 小さな「改善行動」を一緒に決める
分析で見つかった根本原因に対して、何をどう変えていくか、具体的な行動計画を立てましょう。このとき、一度に大きな目標を立てるのではなく、明日からでもすぐにできる小さな行動に焦点を当てることが効果的です。
- 悪い例:「今後はスケジュール管理を徹底し、二度とミスをしない」(抽象的すぎる)
- 良い例:「複数の案件が重なったときは、まずタスクを書き出して優先順位をつけるようにする」(具体的で実行可能)
行動計画を立てる際には、「SMARTの法則」を参考にするとよいでしょう。
- S (Specific): 具体的な目標
- M (Measurable): 測定可能な目標
- A (Achievable): 達成可能な目標
- R (Relevant): 関連性のある目標
- T (Time-bound): 期限が決まった目標
SMARTの法則に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
3-2. 成長を評価し、次の行動を促す
行動計画は立てっぱなしにせず、上司は部下がどのように行動しているか観察して、積極的にフィードバックを与えましょう。
例:「先週決めた『タスクを書き出す』習慣、ちゃんとできているみたいだね。おかげで今回のプロジェクトはスムーズに進んでいるよ。この調子で続けていこう!」
結果がまだ出ていなくても、改善に向けた努力を評価することで部下の自己肯定感が高まり、「自分は成長している」という実感を持つことができます。この成功体験が、次のチャレンジへの意欲につながっていくのです。
もし再び失敗してしまったとしても、責めるのではなく「前回と比べてどうだった?」「どこに課題があったか一緒に考えよう」と声をかけることで、部下は失敗を恐れず、学び続ける姿勢を身につけていきます。
まとめ:反省を効果的に促す上司が部下を成長させる

昔のCMで「反省だけなら猿でもできる」というキャッチコピーが流行りました。この言葉が示すように、ただ過去を振り返って罪責感に浸るだけでは、人は変わりません。
- 起こった出来事を客観的に整理する
- その事象が起こった原因を探る
- 同じ失敗をしないための具体的な行動計画を立てて実行する
というステップを踏むことで、初めて変化成長することができます。
上司の仕事は、部下を責めることではなくその成長を促すことです。今回ご紹介した方法を通して、部下が自律的に考え、行動できる「反省力」を引き出しましょう。
上司による部下を効果的な反省に導く指導は、部下を「失敗を繰り返す人」から、「失敗から学び、成長する人」へと変えるための重要なスキルです。そして、その過程で、上司と部下の間に深い信頼関係が築かれ、チーム全体の生産性向上にもつながっていくでしょう。
ぜひ、日々のマネジメントにこの考え方やスキルを取り入れて、部下とともに成長していく喜びを感じてください。

私たちオアシス・カウンセリング・サービスでは、さまざまな企業・団体・施設の社内研修に講師を派遣し、上司と部下のコミュニケーションや、社員のメンタルヘルスに関する講義を行なっています。ご興味がある方は、ぜひ以下のページもご覧ください。
→ 「ハートフル・エンゲージメント研修」